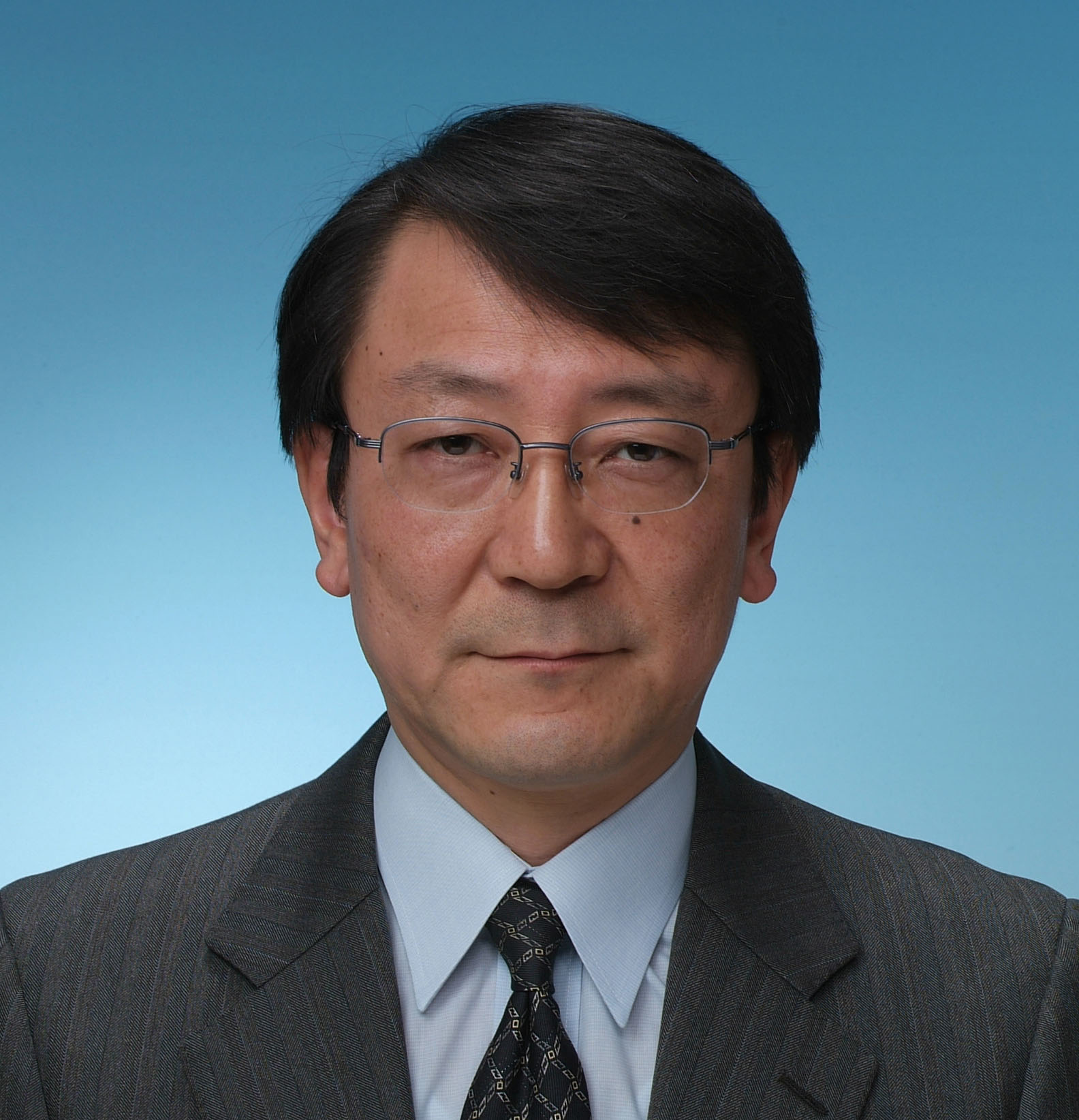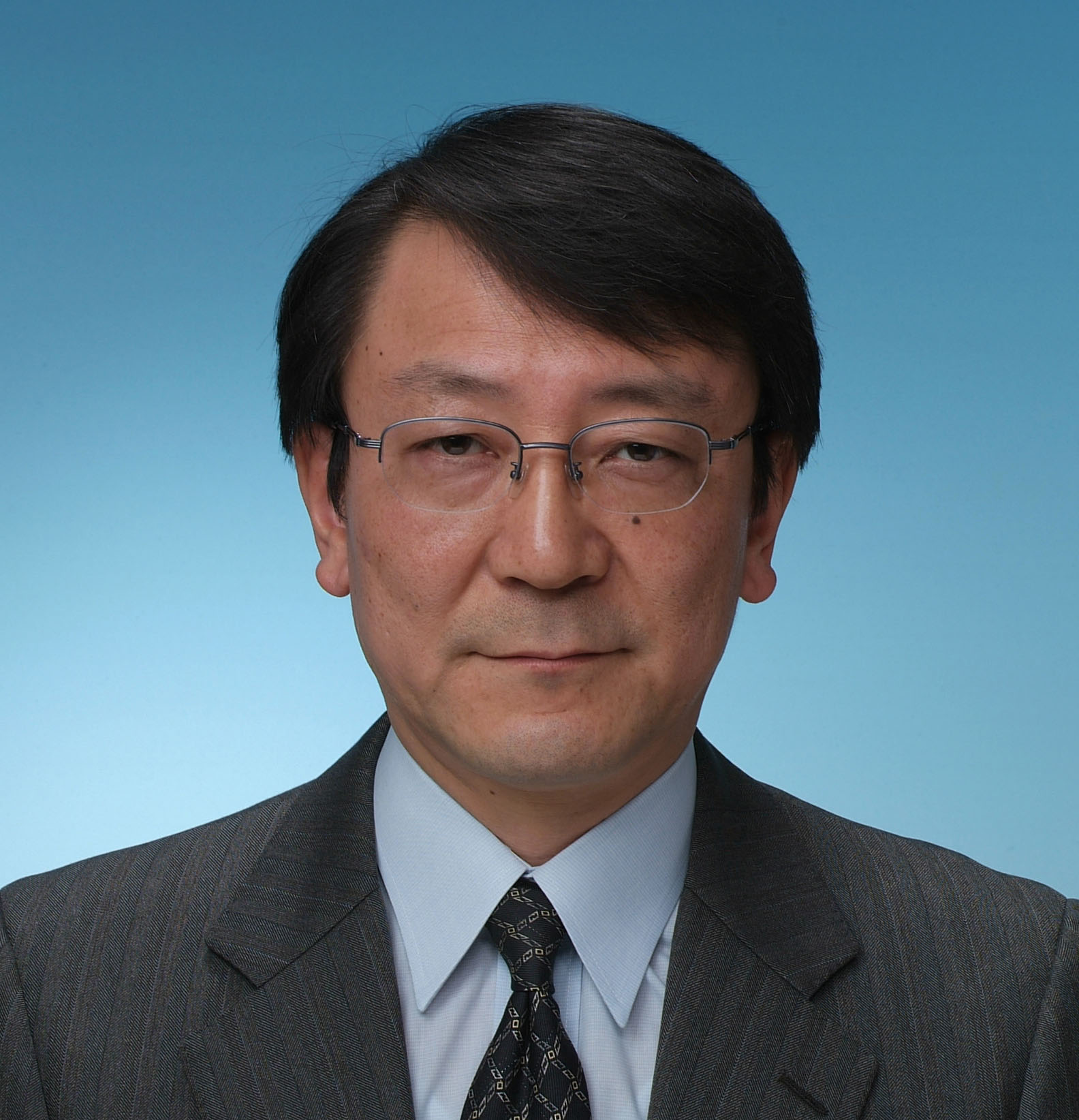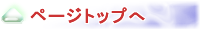|
第10期代表世話人

|
桑畑 進
(大阪大学 大学院工学研究科長・工学部長)
イオン液体研究会のホームページにお立ち寄り下さり、誠にありがとうございます。2023年4月1日から第10期代表世話人をさせて頂くことになりました桑畑でございます。
本会が発足された翌年である2005年に、西川惠子教授(千葉大)が研究代表者を務められた特定領域研究「イオン液体の科学」(2005~2010年)が採択されました。これは世界に先立つイオン液体の大規模な集中的グループ研究であり、私も計画班員として参画させて頂きました。科学研究費補助金(略称:科研費)のひとつである特定領域研究(現在は「学術変革領域研究」がそれに相当)の多くの研究課題は、それまでにあった科学技術をさらに高める、あるいは新側面を開発する、ということが主目的であるのに対し、誰でも扱える安定なイオン液体が登場してから10年程度しか経っていない当時は、謎の液体の正体を明らかにし、応用の可能性を探ることが主たる研究でありました。それゆえ、ミーティングの度に新しい発見が報告され、まさにメンバー全員がワクワクしながら研究をしていました。その時に得られた数多くの成果を基礎とし、経験したワクワク精神を大事にしながら、イオン液体のさらなる可能性を追求する研究者が集い議論する場を提供することが、本イオン液体研究会の大きな役目のひとつであります。
2004年に発足された本会は2023年に20年目を迎えます。最初は「室温でもなぜか液体である不思議な塩」を研究している(関西弁で言うと)けったいな研究者の集団であったかもしれません。しかし、この20年にイオン液体の種類は膨大に増え、designable liquidとしての地位を確固たるものとし、試薬として販売され、比較的容易に入手できる高純度なイオン液体の種類も随分増えました。もはや不思議の段階を脱したイオン液体は、多くの分野で利用方法が検討され、その研究を通してイオン液体に魅力を感じ、本会に入会して頂いている会員の数は現在381名(正会員164名(アカデミック138名,産業界26名),学生会員217名)であり、加えて賛助会員は14社と増加傾向を維持しております。不思議な塩を研究する研究会から始まった本会が、イオン液体を通した不思議な縁をつくる場としての役割を果たし、まだまだ奥深い可能性のあるイオン液体の研究を促進させ、科学のさらなる飛躍の原動力となることを願っております。
本会の代表世話人を務めた方々の一覧を、敬意を込めて以下に表示いたします。
第1期 | 濱口 宏夫 教授 |
第2期・第3期 | 渡邉 正義 教授 |
第4期・第5期 | 西川 惠子 教授 |
第6期 | 伊藤 敏幸 教授 |
第7期 | 大野 弘幸 教授 |
第8期 | 萩原 理加 教授 |
第9期 | 大内 幸雄 教授 |
|
 |
第9期代表世話人

|
大内 幸雄
(東京工業大学 物質理工学院材料系 教授)
この4月より萩原先生の後任として第9期代表世話人を仰せつかりました。
濱口宏夫先生(第一期)、渡邉正義先生(第二・三期)、西川惠子先生(第四・五期)、伊藤敏幸先生(第六期)、大野弘幸先生(第七期)、萩原理加先生(第八期)ら、現在のイオン液体研究の隆盛を支えておられる名だたる先生方の後を引き継ぐ事となりました。元より微力ではありますが、イオン液体研究会の発展に少しでも貢献出来ればと存じます。
2004年の本研究会発足以来、多くの可能性に魅力を感じて集まった研究会の会員数は現在330名(正会員170名(アカデミック142名,産業界28名),学生会員160名)にのぼり,加えて賛助会員企業15社を数えます。昨今のコロナ禍の惨状にあって、討論会や研究会の活動が制限され誠に心苦しい限りですが、会員皆様方と共に成果発表・討論の場、情報交換の場、若手育成の場を盛り立てて行ければと思います。
イオン液体は数多くの学術が交差する境界領域に位置します。
多様な学問体系と多彩な問題意識が融合して数多くの応用展開が生まれ、新たな技術革新に繋がる。逆にその技術革新が予想外の視点を其々の学問体系に還元する、イオン液体研究会とは正にそのようなセレンディピティ(serendipity)を掴むことの出来る貴重な場です。
皆様のご研究の益々の発展を祈念して止みません。
|
 |
第8期代表世話人

|
萩原 理加
(京都大学 教授)
大野弘幸先生の後任として研究会代表世話人を仰せつかりました。
イオン液体研究会は2004年に発足し,研究会の初代代表世話人は濱口宏夫教授(第一期),2代目は渡邉正義教授(第二・三期),3代目が西川惠子教授(第四,五期),4代目は伊藤敏幸教授(第六期)でした。5代目が大野弘幸先生第七期の代表世話人を務められました。私は第八期の代表世話人ということになります。
2004年に発足以来、多くの可能性に魅力を感じて集まったイオン液体研究会の会員数は現在277名(正会員165名(アカデミック135名,産業界30名),学生会員112名)に昇り,加えて賛助会員企業17社を数えます。
20世紀前半に登場したイオン液体ですが、今日の隆盛が始まったのは1990年代の初頭あたりかと思います。それから約30年経つわけですが、その間多くのイオン液体が合成され、研究者の手に比較的容易に高純度のイオン液体が試薬として手に入るようになりました。このことがこの学界を飛躍的に発展させた原動力になったと考えています。今ではイオン液体を対象にしている研究者のみならず、多くの分野でイオン液体を使う研究者が増えています。イオン液体の社会実装もいろいろな分野で、少しずつですが、進んでいます。ただ、学問的には、まだ未知の分野も多く、イオン液体ならではの応用の決定打も出ていません。そのことが逆に、多くの研究者をいまだに捕えて離さない、イオン液体の魅力なのでしょう。イオン液体研究に多くの実績を積み重ねてきた当研究会が、さらなる大きなブレークスルーを生み出すことを願ってやみません。
|
 |
第7期代表世話人

|
大野 弘幸
(東京農工大学 学長)
伊藤敏幸先生の後任として研究会代表世話人を仰せつかりました。
イオン液体研究会は2004年に発足し,研究会の初代代表世話人は濱口宏夫教授(第一期),2代目は渡邉正義教授(第二・三期),3代目が西川惠子教授(第四,五期),4代目は伊藤敏幸教授(第六期)でした。伊藤先生は任期を1年延長され、国際会議などの代表としてご活躍されました。私が2017年度から第七期の代表世話人となりました。代表となるのは得意ではないので、小さくなっておりましたが、ついに指名されてしまいました。折り悪く、東京農工大学の学長職とも重なってしまい、非常に厳しい状況になっております。
2004年に発足以来、多くの可能性に魅力を感じて集まったイオン液体研究会の会員数は現在287名(正会員172名(アカデミック137名,産業界35名),学生会員115名),加えて賛助会員企業16社です。
イオン液体が化学者に広く認知されてきたのはここ20年ほどですが,これまでに多種多様なイオン液体が合成され,徐々に機能デザインの指針も得られるようになってきました。イオン液体研究の中心課題も年とともに変遷し、最近ではバイオ関係の研究が増えてきています。また、研究領域も広がっているため,イオン液体に関する論文数は現在も増加中です。この傾向は、これまでに大きな革命を引き起こした材料の例とよく似ています。本研究会が中心となって、イオン液体研究をさらに活性化させ、イオン液体が社会を変える夢の新材料として大きく羽ばたくことを期待しております。
|
 |
第6期代表世話人

|
伊藤 敏幸
(鳥取大学大学院工学研究科 教授,
鳥取大学グリーン・サスティナルブル・ケミストリー研究
センター長)
西川先生の後任として研究会代表世話人を務めさせていただいています。
イオン液体研究会は2004年に発足し,研究会の初代代表世話人(第一期)は濱口宏夫元東京大学教授(現在,台湾国立交通大学教授),2代目は渡邉正義教授(第二・三期),3代目が西川惠子教授(第四,五期),昨年4月に筆者が4代目(第六期)を引き継ぎました。研究会の会員数は現在306名(正会員175名(アカデミック134名,産業界41名),学生会員131名),加えて賛助会員企業17社という構成です。
イオン液体が化学者に広く認知されてきたのは,この20年ですが,ひとたび認知されるや多種多様なイオン液体が合成され,文献記載のイオン液体はすでに1300種以上になります。イオン液体研究の発展を牽引した合成化学分野,電池やキャパシタ分野に関しては2009年をピークに減少傾向にありますが,新たな研究領域が広がっているため,イオン液体に関する論文数は現在も右肩上がりで増加中です。2015年に韓国済州島で開催されたCOIL-6ではバイオ関連の話題が多数発表されましたが,COIL-1やCOIL-2の頃にはそのような話題はほとんどありませんでした。このように,研究の潮流が常にドラスティックに変化していることもイオン液体研究の特徴に挙げられます。
昨年はNHKの番組サイエンスZEROで「液体化学の革命児イオン液体に迫る!」が7月5日と11日に放映されました。関西大学石川正司教授,九州大学後藤雅宏教授と筆者が出演しています。アーカイブでご覧いただけると幸いです。
(http://www.nhk.or.jp/zero/contents/dsp510.html) |
 |
第4期・第5期代表世話人
 |
千葉大学
西川惠子
第4期の『イオン液体研究会』の代表世話人をさせていただくこととなりました。第1期の濱口宏夫代表世話人、第2、3期の渡邉正義代表世話人の後を引き継ぎ、本研究会の発展に少しでも貢献したいと思っております。
私は、イオン液体の出現を『液体科学の革命』と位置づけております。水や有機溶媒などの従来の液体と全く異なるユニークな性質を有し、物性や機能を様々にデザインできるからです。新規液体としての基礎研究に始まり、新規性を生かした反応場・物質分離場・電気化学場としての開発と利用、デザインを含んだ機能性液体としての利用や応用など、その広がりはとどまるところを知りません。これまでにも物質科学におけるパラダイム転換と位置づけられる物質群の出現が幾度かありました。新たな物質観が誕生し、大きな展開が後を追い、一つの研究分野に成長し、産業界で活躍していく。イオン液体は、まさに物質科学におけるパラダイムの転換の一つと位置づけられると思います。
イオン液体の研究内容も多岐にわたり、また研究者も産官学の広い範囲にわたります。『既存の学会や分野また所属の枠に囚われることなく、イオン液体の基礎と応用に興味を持つ方々に広く情報交流の場を提供しよう』と、本研究会は平成16年度に立ち上がりました。時を同じくして、文部科学省の支援を受けてイオン液体に関する大きなプロジェクトである科学研究費補助金特定領域研究『イオン液体の科学』が採択されました。本研究会およびこの特定領域研究は、日本におけるイオン液体研究推進の両輪として、大きな役割をはたして参りました。
特定領域研究は平成22年3月に終了し、事後評価において最高ランクの評価(「特定領域の設定目標に照らして、期待以上の成果が有った」)をいただきました。『イオン液体の基礎科学的理解に重点を置きながら、物理化学・有機化学・材料化学の研究者達が連携して新しい化学の分野を開拓することに成功しており、その波及効果は他分野にまで及んでいる』という具体的な評価もいただきました。我々は、イオン液体のユニークさを、それが何故発現するのかを多くの現象で明らかにし、イオン液体ならではの現象や反応を数多く見出し、多くの機能発現・開拓の芽を芽吹かせることに成功してきたと言えるでしょう。すなわち、イオン液体に対して、『液体の地位と役割を確立』し、イオン液体を一つの研究分野として、確実に、日本に根付かせることができたと思います。特定領域研究『イオン液体の科学』は、終了いたしましたが、その成果は『イオン液体研究会』に引き継がれ、大輪の花を咲かすことに成ると思われます。また、そのように成るように、我々イオン液体研究者は努力しなければならないと思います。
本研究会は、構成メンバー300人足らずの小さな集まりですが、化学の様々な分野を専門としている広範な方々の集まりです。メンバーは大学にとどまらず、企業の研究者の方々が数多く参加されていることも特徴であり、強みと申せましょう。こうした学際性と多様性に富んだ強みを生かして、本研究会ならではの活動と情報交流の場を提供していきたいと思います。世話人で話し合い、このためにまず、年1回の討論会(名称:イオン液体討論会)と1回の研究集会を定例で行うことに決めました。平成22年度は、鳥取で伊藤敏幸先生のお世話で討論会を(平成23年1月16、17日)、岩田耕一先生のお世話で学習院大学で研究集会(平成23年3月)に行います。また、平成23年7月には、本研究会監修の単行本『イオン液体の科学 -新世代液体への挑戦-』が丸善出版より刊行される予定です。
イオン液体研究会の事務組織について、簡単に説明させていただきます。本研究会の会員管理およびホームページの管理、お知らせのメール発信は、(株)ポラリス・セクレタリーズ・オフィスに委託しております。ホームページやメールなどでも、最新の情報が皆様にお届けできるよう、力を尽くしていきたいと思っております。
特定領域研究が終了し、一つの節目を迎えました。『イオン液体研究会』が日本におけるイオン液体研究の情報交流のただ一つの拠点となります。研究会は、皆様のご参加とご協力で初めて成り立つものです。イオン液体研究の発展のためにも、皆様の変わらぬご協力を宜しくお願いいたします。
|
 |
第3期代表世話人
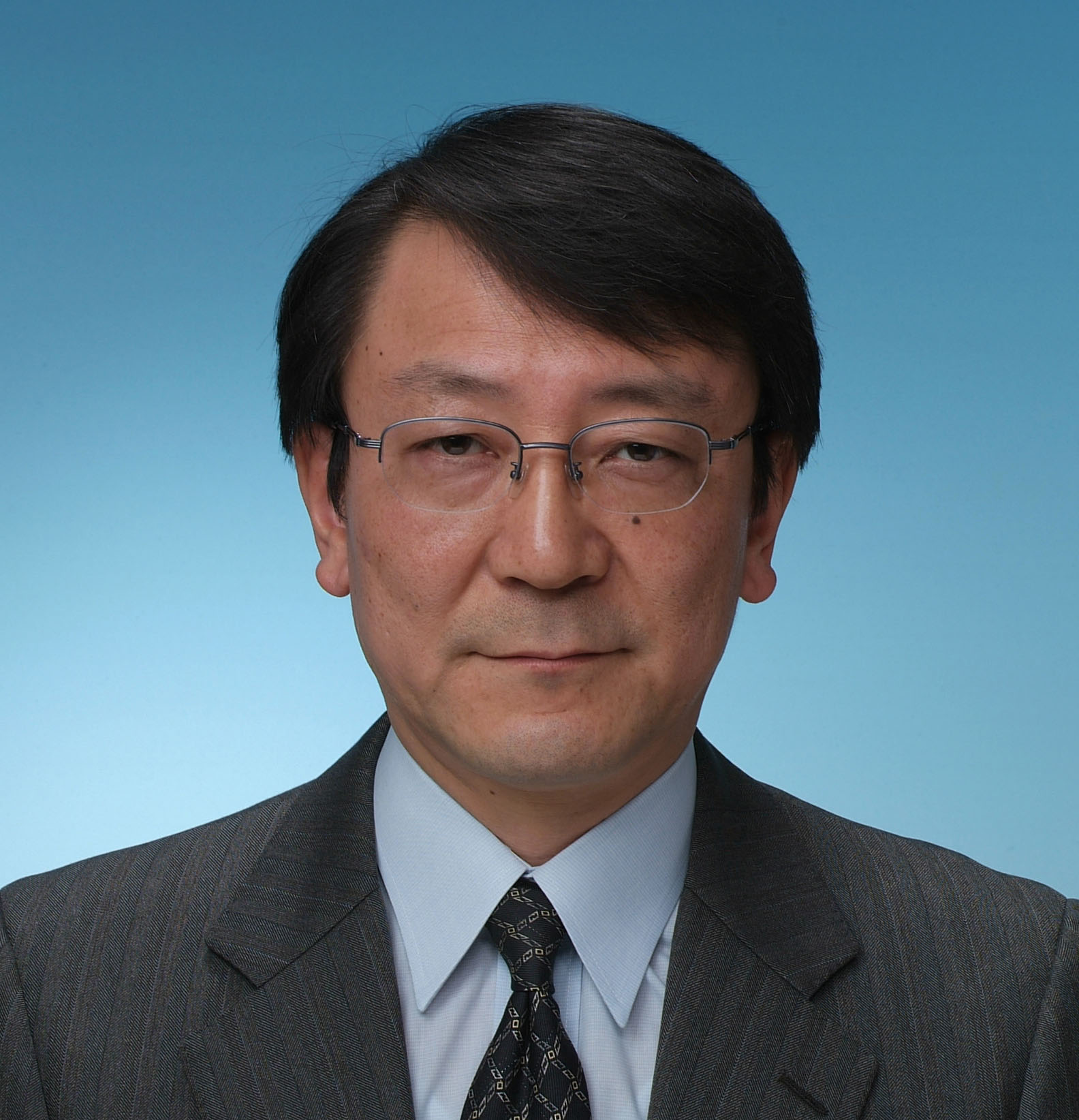 |
横浜国立大学
渡邉正義
平成20年4月より2年間、第2期に引き続き「イオン液体研究会」 の代表世話人をさせて頂くことになりました。本研究会の発展に少しでも貢献したいと思っております。
イオン液体の研究は本当に多岐に渡っていて、しかも現在とてもホットな領域です。本研究会を平成16年に設立したのも、 「既存の学会の枠にとらわれることなく、イオン液体の基礎と応用に興味をもつ産官学の方々に広く情報交流の場を提供しよう」 ということがきっかけでした。現在もその趣旨は変わっておらず、 「小粒ながらピリリと辛いユニークな学術団体」 を目指したいと思っております。
この研究会発足に期を合わせ、大学関係者の間で文部科学省の援助を受けたイオン液体に関する大きなプロジェクト研究を立ち上げようという機運が盛り上がりました。幸いなことに、千葉大学、西川教授を代表として 平成17-21年の特定領域研究 に採択され、参加研究者50グループのイオン液体に関するプロジェクト研究 「イオン液体の科学」 が始まりました。総研究予算は16億円以上になる予定です。このプロジェクト研究が継続している間は、イオン液体研究会とも密接に交流し、会員の皆様に最新情報の提供および交換を図っていきたいと思っています。また、 平成19年の8月には「第2回のイオン液体国際会議(COIL-Ⅱ)」がパシフィコ横浜で開催 され、500名以上の参加者を得て大盛会となりました。平成21年5月31日~6月4日には、オーストラリア、ケアンズ市でCOIL-IIIが開催される予定です。
イオン液体研究会の事務組織についても少し説明致します。現在、 本研究会の会員管理 (入脱会・会費納入の事務)に関しましては (株)ポラリス・セクレタリーズ・オフィスに委託 しておりますのでご協力下さい。また、研究会の ホームページは横浜国立大学で管理 し、最新情報の更新や、会員の皆様の情報交換に少しでも役立てるよう努力を続けて参ります。ご意見・ご要望等ございましたら管理者までご連絡下さい。
イオン液体研究会は、賛助会員、正会員、学生会員を合わせても300名程度の小さな学術団体です。しかし、小さいからこそより親密な交流、機動力のある活動ができると思っています。理想は 「イオン液体という極めてユニークで面白い物質を囲む、個性的でかつチャレンジングな研究会」 です。会員の皆様方のご協力とご参加をお願い致します。 |
 |
第2期代表世話人
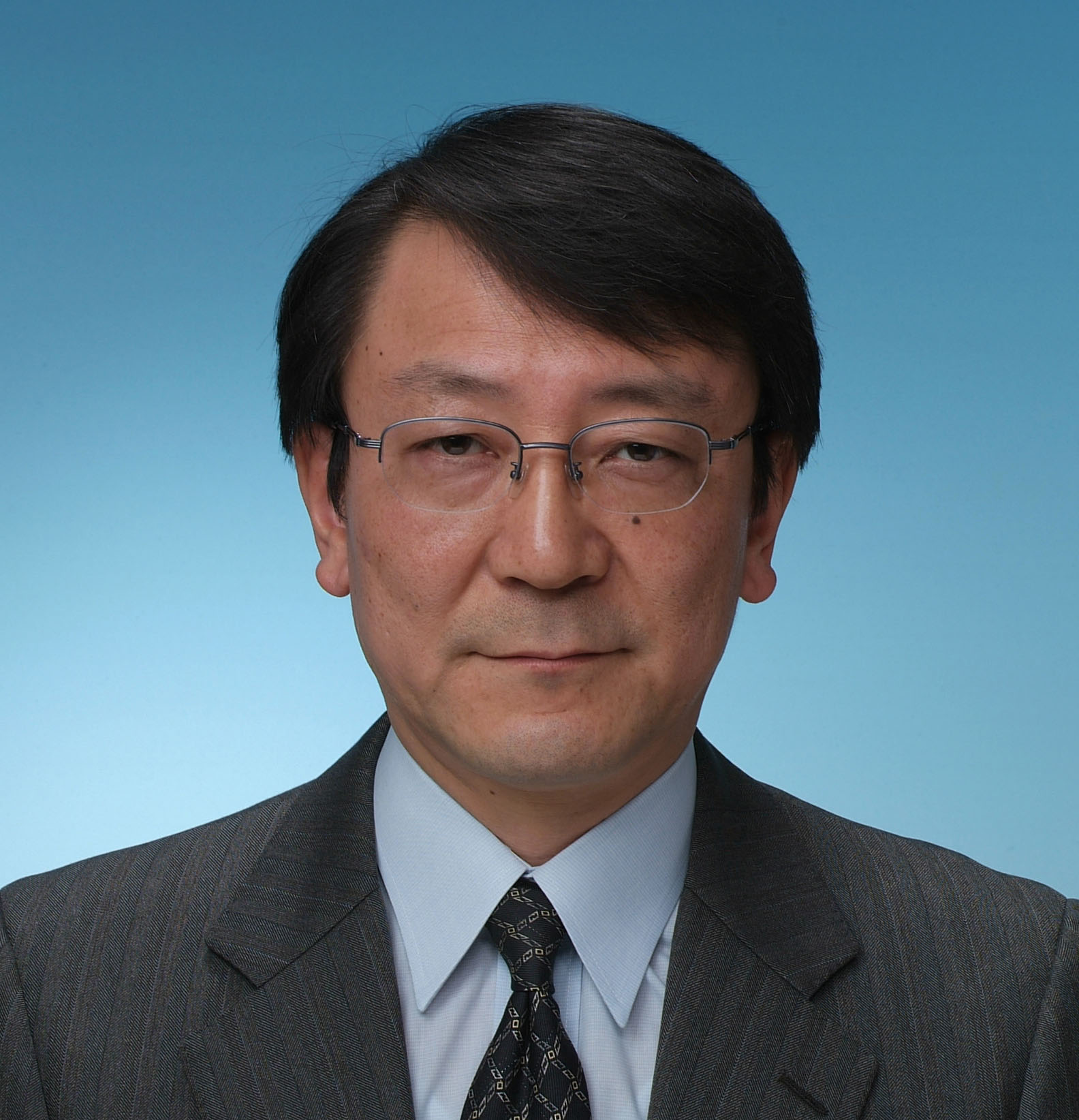 |
横浜国立大学
渡邉正義
平成18年4月より2年間、 「イオン液体研究会」 の代表世話人をさせて頂くことになりました。初代代表の東京大学、濱口教授の後を継ぐ形で、本研究会の発展に少しでも貢献したいと思っております。
イオン液体の研究は本当に多岐に渡っていて、しかも現在とてもホットな領域です。本研究会を平成16年に設立したのも、 「既存の学会の枠にとらわれることなく、イオン液体の基礎と応用に興味をもつ産官学の方々に広く情報交流の場を提供しよう」 ということがきっかけでした。現在もその趣旨は変わっておらず、 「小粒ながらピリリと辛いユニークな学術団体」 を目指したいと思っております。
この研究会発足に期を合わせ、大学関係者の間で文部科学省の援助を受けたイオン液体に関する大きなプロジェクト研究を立ち上げようという機運が盛り上がりました。幸いなことに、千葉大学、西川教授を代表として 平成17-21年の特定領域研究 に採択され、参加研究者50グループのイオン液体に関するプロジェクト研究 「イオン液体の科学」 が始まりました。総研究予算は16億円以上になる予定です。このプロジェクト研究が継続している間は、イオン液体研究会とも密接に交流し、会員の皆様に最新情報の提供および交換を図っていきたいと思っています。また、 平成19年の8月には「第2回のイオン液体国際会議(COIL-Ⅱ)」がパシフィコ横浜で開催 されることが決まっています。平成17年オーストリアのザルツブルグで開かれた第1回の会議で400名以上の参加者を得たので、横浜での会議はそれ以上の盛会になると期待しています。
イオン液体研究会の事務組織についても少し説明致します。現在、 本研究会の会員管理 (入脱会・会費納入の事務)に関しましては (株)ポラリス・セクレタリーズ・オフィスに委託 しておりますのでご協力下さい。また、研究会の ホームページは横浜国立大学で管理 し、最新情報の更新や、会員の皆様の情報交換に少しでも役立てるよう努力を続けて参ります。ご意見・ご要望等ございましたら管理者までご連絡下さい。
イオン液体研究会は、賛助会員、正会員、学生会員を合わせても300名程度の小さな学術団体です。しかし、小さいからこそより親密な交流、機動力のある活動ができると思っています。理想は 「イオン液体という極めてユニークで面白い物質を囲む、個性的でかつチャレンジングな研究会」 です。会員の皆様方のご協力とご参加をお願い致します。 |
|