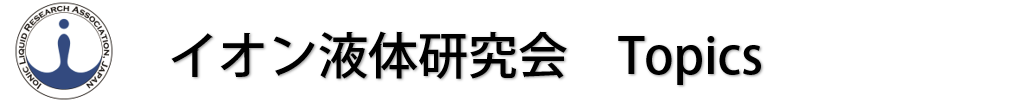Topics
2024.09.30 circular No.23
イオン液体を用いたジャイロイド構造設計東京農工大学大学院 工学研究院 生命機能科学部門
(工学府 生命工学専攻)
一川 尚広
このような場で、これまで私が推進してきた研究を紹介する機会をいただき、イオン液体研究会サーキュラーの編集委員の皆様に深く感謝いたします。このTopics記事では、これまでの私が助教または准教授に昇任してから進めてきたイオン液体研究を紹介させていただきます。
『液晶』というと『ディスプレイ』を思い浮かべる方がほとんどではないかと思われますが、実際には『液晶』とは、液体の『液』と結晶の『晶』を合わせて作られた単語であり、液体と結晶(固体)の『中間の状態』を示す言葉である。ディスプレイとしての応用が圧倒的に花咲き、社会にも大きなインパクトを及ぼし、科学者以外にも認知される単語となったことは凄いことである。『液晶』という状態の1つの応用先としてディスプレイがあることは間違いないが、それ以外の様々な応用可能性が『液晶』には潜んでいる。液晶相を示す物質または形成される分子集合構造の形態に応じて様々に分類することができるが、その中でも、ナノ相分離型の液晶は、分子レベルでの相分離を駆動力として多様な次元性を持った分子集合構造を形成するソフトマターである(図1)1-3。私は、ナノ相分離型液晶が形成する液晶相の一つである双連続キュービック液晶相に着目して長らく研究を推進してきた4-7。特に、私が助教として大野・中村研に着任した時、大野・中村研で開発されてきた非常に個性的なイオン液体を数多く目の当たりにし、これらの個性的なイオン液体の特徴を活かした自己組織性(液晶性)イオン液体の研究を進めてきたので、イオン液体の種類の観点から研究テーマを分類して、以下で紹介させていただきます。

図1. ナノ相分離型の液晶が形成する様々なナノ構造
2.学生時代の研究を振り返って
2.1.Zwitterionを用いた双連続キュービック液晶
カチオンとアニオンが共有結合で連結したZwitterionは単独では融点の高い結晶性の固体であるが、LiTf2NまたはHTf2Nなどを当モルで混合すると、固体と固体を混ぜているにも関わらず液体となることを大野らが2000年代の初頭に見出した8,9。これはZwitterionとLiTf2N(またはHTf2N)の間でHSAB則に従ったイオン交換が起こり、イオン液体のようなイオンペアが形成されるためだと考えられる。このようにして得られた液体は、Li+またはH+を選択的に伝導する媒体として興味深い。そのような中、私は、『ZwitterionとLiTf2N(またはHTf2N)がイオンペアを形成する特性』に着目した。この特性を利用すれば、棒状の両親媒性Zwitterionを設計した時、適切なサイズのアニオンを持つ酸またはリチウム塩を加えることで、両親媒性Zwitterion/酸(またはリチウム塩)が形成する複合体の『疑似的な分子実効形状』を棒状から紡錘状まで自在に調整でき、それに伴い、双連続キュービック液晶相の発現を誘起できるのではと考えた(図2)。特に、双連続キュービック液晶相は、スメクチック液晶相とカラムナー液晶相の中間域で発現する液晶相として知られているため、この間となるように添加する酸(またはリチウム塩)の対アニオンのサイズ及び等量を調整することで、多くの両親媒性Zwitterionが目的の双連続キュービック液晶相を形成することが分かった10-19。

図2. 両親媒性Zwitterionを用いたナノ相分離型液晶相の制御
2.2.ジャイロイド極小界面を用いた三次元プロトン伝導
両親媒性Zwitterion(例えば、図3aのPyZI)とHTf2Nの複合体10は双連続キュービック液晶相を発現し、ジャイロイド構造を形成する(図3b)。双連続キュービック液晶相の形成は偏光顕微鏡観察・X線回折測定などで同定することができる。例として、PyZI/HTf2N複合体がカラムナー液晶相から双連続キュービック液晶相へと転移する過程を偏光顕微鏡を通して観察した時のテクスチャの変化を図3cに示す。異方的な構造を持つカラムナー液晶相の時には、液晶相特有の光学組織が観察されるが、光学的に等方な双連続キュービック液晶相への転移が始まると複屈折が消失していき、完全に真黒な状態へと変化していく。
PyZI /HTf2N複合体が形成するジャイロイド構造において、両親媒性Zwitterionの末端のスルホネート基は全てジャイロイド極小界面上に配列している(図3b)。また、その親水的な界面は、ピリジニウムカチオンとTf2Nから構成される疎水的なイオンペア(疎水性レイヤー)によってサンドイッチされた構造になっているため、少量の水を添加すると、ジャイロイド極小界面に沿ってのみ水分子が取り込まれ、極めて薄いがマクロに連続した水の三次元ナノシートが形成されるのではないかと考えた。また、この三次元ナノシートに沿って高速なプロトン伝導が生じるのではないかとも期待した。実際に、少量の水を含ませた化合物に対して交流インピーダンス法によりイオン伝導度を評価すると、含水率の上昇に伴い、急激な伝導度の上昇を見出すことができ、高速なプロトン伝導を実現できることを明らかとした10。

図3. a) 両親媒性Zwitterion (PyZI)とHTf2Nの分子構造、b) PyZI/HTf2N複合体が形成する分子集合構造、c) カラムナー液晶相から双連続キュービック液晶相へと転移する過程を偏光顕微鏡観察した時のテクスチャの変化
次に、両親媒性Zwitterionが形成する分子集合構造を固定化することを目的として、重合性官能基を導入した両親媒性Zwitterionを設計した(図4a左)13。この分子も酸および適量の水の存在下、双連続キュービック液晶相を発現した。双連続キュービック液晶状態でin situ重合したところ、自立性の高分子膜を得ることができた(図4a右)。膜の含水率は湿度コントロールなどで調整できた。膜内のナノ構造をSheffield大学のZeng博士らとシンクロトロンX線散乱測定により調べたところ、図4bに示すような三次元電子密度マップを作ることに成功した。また、含水率が変化してもジャイロイド構造を維持していることも分かった。三次元電子密度マップを比較したところ、含水率の上昇に伴い、ジャイロイド極小界面上の電子密度が最密(紫)から少し低くなる(青)ことが分かり、界面に沿って水分子が取り込まれていることを示唆する結果を得ることができた。
膜内の水分子のダイナミクスがプロトン伝導機構に強く関与すると考え、総合科学研究機構(CROSS)中性子科学センターの山田武博士と協力して、中性子準弾性散乱測定により水分子のダイナミクスを解析した。膜内の水分子は全て結合水として存在するものの、局所的な運動をしていることが分かった。これらの結果より、膜内のプロトン伝導機構が高速な界面プロトンホッピング伝導機構であることを明らかとした18。スルホネート基を高密度に配列することで、プロトンがホッピングする際の活性化エネルギーが極めて低減されて、このような機構が働いたと考察している。今後、このような設計が、例えばPFASフリーなプロトン伝導電解質膜や高温または低温でも駆動する燃料電池の開発などに貢献できればと考えている。

図4. a) 我々が設計した重合基をアミノ酸イオン液体を用いたリオトロピック液晶有する両親媒性Zwitterionとそれを用いたジャイロイド構造膜、b) ジャイロイド構造膜中の電子密度マップの含水率依存性
3.アミノ酸イオン液体を用いたリオトロピック液晶
液晶の中には、溶媒と両親媒性分子の混合物からなるものが存在し、それらはリオトロピック液晶と呼ばれる。主に、水や有機溶媒を溶媒とした系がほとんどであるが、イオン液体を溶媒としたリオトロピック液晶も2000年代初頭から報告され始めた20-22。イオン液体と両親媒性分子は混ざりあわない組み合わせも多く、イオン液体の選択が極めて重要である。そのような中、私は大野研で2005年に開発された天然アミノ酸をアニオンとして有するイオン液体(アミノ酸イオン液体)23,24に着目した。フッ素系アニオンを有する汎用のイオン液体と比較して、アミノ酸イオン液体は高い水素結合能を有している点が特徴である。水が優れたリオトロピック液晶溶媒として機能する理由の1つとして、水分子の高い水素結合能が挙げられる。この事実を踏まえ、アミノ酸イオン液体はイオン液体の中でも優れた自己組織化(促進)溶媒となるのではないかと着想した。更に、アミノ酸イオン液体のアニオン側鎖Rを調整することで、溶媒の水素結合能を調整することができるため、『溶媒設計』により両親媒性分子の自己組織化をコントロールする方法論を構築できるのではないかと着想した(図5)。実際に様々な両親媒性分子とアミノ酸イオン液体を組み合わせて成分比によって現れる液晶相をまとめた相図を作製していくと、この着想が概ね妥当であることが分かった。アニオン種の選択で得られる相図は大きく変化し、目的としている双連続キュービック液晶相の発現の有無も変化することが分かった25-27。

図5. アミノ酸イオン液体を溶媒としたリオトロピック液晶設計
4.アトロプ異性化を利用した捩じれ構造設計
双連続キュービック液晶が形成するジャイロイド構造は、ダブルジャイロイド構造であり、右捩じれと左捩じれのネットワークが入れ子になった構造である28,29。このような分子集合構造を誘起するためには、分子自体も捩じれを有していた方が良いのではないかと考え、捩じれ構造の導入に挑戦した。具体的には、図6aに示したようにベンゼン環に二つのイミダゾリウム環が結合した構造を設計すると、Rのかさ高さ次第で、ベンゼン環とイミダゾリウム環を結ぶC-N結合の回転が抑制され、軸不斉を形成する(アトロプ異性化)。もう少し具体的に説明すると、2つのイミダゾリウム環の捩じれの向きの組み合わせに従って、R体、S体、およびmeso体の3種類の立体異性体を形成する。このような立体異性体の形成は、1H NOESY NMRによる1H-1H 間の相関を観測することにより明らかにすることができた30,31。この特異なイオン骨格を頂点とした扇形のイオン性液晶分子を設計したところ、アニオン種や扇形部位のアルキル鎖の長さに応じて、目的の双連続キュービック液晶相を形成することが分かった30,31。液晶状態における三次元電子密度マップを構築したところ、図6b,cに示すような一辺の長さが約9 nmのジャイロイド構造を可視化することに成功した。イオン性部位が三次元のナノチャンネル(橙色)を形成し、アルキル鎖末端が青色で示した三次元極小界面上に位置するように配列してこのような構造が出来上がっていると考えられる。バルク状態における『分子自体の捩じれ』と『捩じれた分子集合構造(ダブルジャイロイド構造)』の因果関係を明確にするのは非常に困難であるが、今後もこのような分子のコンフォメーションに着目した液晶設計と機能設計に挑戦していきたい。また、このような素材は、イオン性の三次元ナノチャンネルを有しているので、CO2などを選択的に取り込み透過するガス分離膜などへの応用を期待している。

図6. a) アトロプ異性化能を有するイオン性骨格、b, c) このイオン構造を有する扇形イオン性液晶分子が形成するジャイロイド構造中の電子密度マップ(cは電子密度の高い領域と低い領域のみを可視化している。)
5.LCST型イオン液体を利用した凝集誘起発光のOn/Off制御
大野らは2007年にある種のホスホニウム塩型イオン液体が水中でLCST型相転移を示すことを見出した32。それ以降、当時、大野・中村研に所属していた河野雄樹博士(現、産総研主任研究員)を中心として精力的に研究が進められ33-35、世界的にもこのイオン液体のLCST型相転移挙動を研究する科学者が増え続けている36-38。この現象は、温度上昇に伴うホスホニウムカチオンからの脱水和とそれに伴うイオン凝集が駆動力であると考えられる。一相 $21C6 二相相転移を利用した分離や抽出などに関する研究が注目されてきたが、我々は、この現象を『物質(分子)の凝集/解離の自在制御』に使えるのではないかと着想した。そこで、一つの例として、様々な凝集誘起型の機能の中でも、『凝集誘起発光(Aggregation-Induced Emission: AIE)』に着目した39,40。AIEは、ある種の芳香族化合物が溶液中で消光するが、固体状態では強く発光する現象のことであり、Ben Zhong Tangらが2000年代の初頭に見出した現象である39。通常は、AIE化合物を良溶媒に溶かし、少しずつ貧溶媒を加えて析出する過程で発光特性のOff→Onを追跡する実験を行う。このようなAIE挙動をイオン液体のLCST型相転移挙動と連動させることができないかと考え、図7aに示したようなTetraphenylethyleneをアニオン骨格に導入したホスホニウム塩を設計した41。このホスホニウム塩は、室温では結晶で、水に可溶であるが、このホスホニウム塩を溶かした水溶液を加熱していくと約39 °Cで白濁し(イオン液体濃度によって相転移温度は変化する)、ホスホニウム塩が水和イオン液体の微小液滴として析出し始める。この白濁状態のサンプルに励起光を照射すると、AIEに伴う発光を観察することができた(図7b)。単なる光の散乱でないことは、発光波長からも明らかであった。Tetraphenylethylene骨格を持たない類似のホスホニウム塩との比較からも、Tetraphenylethylene誘導体アニオンからのAIE発光であることを確証付けることができた。このようにLCST型相転移に伴い発光特性のOn/Offを制御することに成功した(図7b)。今後も、このようなイオン液体の動的な挙動を活かした様々な凝集誘起型の機能制御に挑戦していきたい。

図7. a) 我々が設計したTetraphenylethylene誘導体アニオンを有するホスホニウム塩型のイオン液体、b) このイオン液体が水中でLCST型相転移挙動に伴いAIE発光のOff $21C6 Onを変化する様子
9.おわりに
私自身は2005年から液晶化学の研究をスタートし、これまでイオン液体を基盤として、良く言えば特異な、悪く言えば変な素材を色々と生み出してきた。この間、イオン液体に大変ワクワクを与えられてきたなと感じており、イオン液体には感謝するばかりである。もちろん研究指導してくださった恩師の皆様、一緒に研究に挑戦してくれた学生さん、共同研究者の皆様、またイオン液体コミュニティの皆様にも深く感謝するばかりです。ジャイロイド構造を偏光顕微鏡で観察すると複屈折が無く、真っ暗である。この真っ暗の先にどのような輝かしい機能・応用・可能性が秘められているか、私自身にも分からないが、これからも今回紹介させていただいたような研究をさらに推進し、『液晶』という単語を再度、世界に響き渡らせたい!
引用文献
- T. Kato, N. Mizoshita, and K. Kishimoto, Angew. Chem. Int. Ed., 45, 38 (2006)
- T. Kato, M. Yoshio, T. Ichikawa, B. Soberats, H. Ohno, and M. Funahashi, Nat. Rev. Mater., 2, 17001 (2017)
- J. Uchida, B. Soberats, M. Gupta, and T. Kato, Adv. Mater., 34, 2109063 (2022)
- T. Ichikawa, M. Yoshio, A. Hamasaki, T. Mukai, H. Ohno, and T. Kato, J. Am. Chem. Soc., 129, 10662 (2007)
- T. Ichikawa, M. Yoshio, A. Hamasaki, J. Kagimoto, H. Ohno, and T. Kato, J. Am. Chem. Soc., 133, 2163 (2011)
- M. Henmi, K. Nakatsuji, T. Ichikawa, H. Tomioka, T. Sakamoto, M. Yoshio, and T. Kato, Adv. Mater., 24, 2238 (2012)
- T. Ichikawa, M. Yoshio, S. Taguchi, J. Kagimoto, H. Ohno, and T. Kato, Chem. Sci., 3, 2001 (2012)
- M. Yoshizawa, M. Hirao, K. I-Akita, and H. Ohno, J. Mater. Chem., 11, 1057 (2001)
- M. Yoshizawa and H. Ohno, Chem. Commun., 1828 (2004)
- T. Ichikawa, T. Kato, and H. Ohno, J. Am. Chem. Soc., 134, 11354 (2012)
- T. Matsumoto, T. Ichikawa, J. Sakuda, T. Kato, and H. Ohno, Bull. Chem. Soc. Jpn., 87, 792 (2014)
- T. Kobayashi, T. Ichikawa, T. Kato, and H. Ohno, Adv. Mater., 29, 1604429 (2017)
- T. Kobayashi, Y. Li, A. Ono, X. Zeng, and T. Ichikawa, Chem. Sci., 10, 6245 (2019)
- T. Ichikawa, T. Kato, and H. Ohno, Chem. Commun., 55, 8205 (2019)
- A. Maekawa, T. Kobayashi, and T. Ichikawa, Polym. J., 53, 463 (2021)
- T. Kobayashi, Y. Li, Y. Hirota, A. Maekawa, N. Nishiyama, X. Zeng, and T. Ichikawa, Macromol. Rapid Commun., 42, 2100115 (2021)
- H. Oshiro, T. Kobayashi, and T. Ichikawa, Mol. Syst. Des. Eng., 7, 1459 (2022)
- T. Ichikawa, T. Yamada, N. Aoki, Y. Maehara, K. Suda, and T. Kobayashi, Chem. Sci., 15, 7034 (2024)
- T. Ichikawa, Polym. J., 49, 413 (2017)
- N. Kimizuka and T. Nakashima, Langmuir, 17, 6759 (2001)
- R. Atkin and G. G. Warr, J. Am. Chem. Soc., 127, 11940 (2005)
- T. L. Greaves and C. J. Drummond, Chem. Soc. Rev., 37, 1709 (2008)
- K. Fukumoto, M. Yoshizawa, and H. Ohno, J. Am. Chem. Soc., 127, 2398 (2005)
- H. Ohno and K. Fukumoto, Acc. Chem. Res., 40,1122 (2007)
- T. Ichikawa, K. Fujimura, M. Yoshio, T. Kato, and H. Ohno, Chem. Commun., 49, 11746 (2013)
- K. Fujimura, T. Ichikawa, M. Yoshio, T. Kato, and H. Ohno, Chemistry-An Asian J., 11, 520 (2016)
- T. Ichikawa, T. Kato, and H. Ohno, Chem. Commun., 55, 8205 (2019)
- C. Dressel, T. Reppe, M. Prehm, M. Brautzsch, and C. Tschierske, Nat. Chem., 6, 971 (2014)
- C. Dressel, F. Liu, M. Prehm, X. Zeng, G. Ungar, and C. Tschierske, Angew. Chem., Int. Ed., 53, 13115 (2014)
- N. Uemura, T. Kobayashi, S. Yoshida, Y. Li, K. Goossens, X. Zeng, G. Watanabe, and T. Ichikawa, Angew. Chem., Int. Ed., 59, 8445 (2020)
- T. Ichikawa, S. Obara, S. Yamaguchi, Y. Tang, T. Kato, and X. Zeng, Chem. Commun., 2024, DOI: 10.1039/D4CC03002H
- K. Fukumoto and H. Ohno, Angew. Chem., Int. Ed., 46, 1852 (2007)
- Y. Kohno, H. Arai, S. Saita, and H. Ohno, Australian J. Chem., 64, 1560 (2011)
- Y. Kohno and H. Ohno, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 5063 (2012)
- Y. Kohno and H. Ohno, Chem. Commun., 48, 7119 (2012)
- R. Wang, W. Leng, Y. Gao, and L. Yu, RSC Adv., 4, 14055 (2014)
- A. Nitta, T. Morita, K. Nishikawa, and Y. Koga, Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 16888 (2017)
- H. Kang, D. E. Suich, J. F. Davies, A. D. Wilson, J. J. Urban, and R. Kostecki, Commun. Chem., 2, 51 (2019)
- Y. Hong, J.W. Y. Lama, and B. Z. Tang, Chem. Commun., 4332 (2009)
- J. Luo, Z. Xie, J. W. Y. Lam, L. Cheng, H. Chen, C. Qiu, H. S. Kwok, X. Zhan, Y. Liu, D. Zhu, and B. Z. Tang, Chem. Commun., 1740 (2001)
- H. Iwasawa, D. Uchida, Y. Hara, M. Tanaka, N. Nakamura, H. Ohno, and T. Ichikawa, Adv. Opt. Mater., 11, 2301197 (2023)